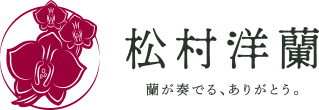【病気・予防と初動処置】胡蝶蘭の育て方
胡蝶蘭も病気にかかることがあります。
そして、胡蝶蘭の免疫が下がることでより病気にかかりやすくなってしまうのです。
人間とおなじですね。
・予防の方法が気になる
・病気になったらまず何をすればいいのか知りたい
そんな方向けに、今回は胡蝶蘭の健康を考える「病気の予防と初動処置」についてお話します。
病気を予防する方法
健康で丈夫な胡蝶蘭を育てることがなにより大切です。
予防のためには、以下5点を日常から心がけましょう。
- 最低10度~最高30度の適温にする
- レースカーテン越しのやわらかい光を当てる
- 風通しをよくする ※冷房や暖房機の乾燥風はNG
- 水はタイミングをみて株元に適量を
- 急激な変化を起こさない
これらは胡蝶蘭の基本の育て方でもあります。
日頃から取り組み、胡蝶蘭を元気に保ちましょう。
▼胡蝶蘭を楽しく育てる基本編「開花中の管理」
病気にかかったら最初にやること
「なにか変だな?いつもと様子が違うな?」
というような異常を感じたらできるだけはやめに行動しましょう。
時間が経つにつれて、病気は深くまで進行してしまいます。
取り返しがつかなくなる前に適切な対処をすれば、回復する確率が高まります。
育てた胡蝶蘭の元気がないとつい焦ってしまいがちですが、ハラハラする気持ちをグッとこらえて冷静な対処を心がけましょう。
1. 病気の株は隔離して管理しましょう
胡蝶蘭は寄せ植えされることが多いお花です。
健康な株の近くに病気の株があると、病気が健康な株へ移ることが懸念されます。
そのため寄せ植えてある場合は、病気の株は健康な株から離して別々に管理をしましょう。
2. 病気の種類に合う処置をしましょう
誤った処置では病気は治りません。
病気の種類を調べて適切に処置しましょう。
▼胡蝶蘭の病気 対策編はこちら
3. 軽症の場合は消毒したハサミで処置できます
症状が一部しか出ていない軽症の場合は、症状が出ている部分だけをハサミで切り取って処置することができます。
切り口からばい菌が入り別の病気が発生する可能性を防ぐため、ハサミは消毒してから使いましょう。
また切り取った部分はその場に放置せずゴミ箱に捨てましょう。
※消毒方法:ライターでハサミを軽くあぶる等
まとめ
以上「胡蝶蘭の病気 予防編」でした。
日頃から健康で丈夫な株を育て、病気にかかりにくくすること。
それが、病気に対する一番の予防となります。
もし病気の兆候が現れても、慌てず冷静に対処しましょう。
▼胡蝶蘭の病気 対処編はこちら